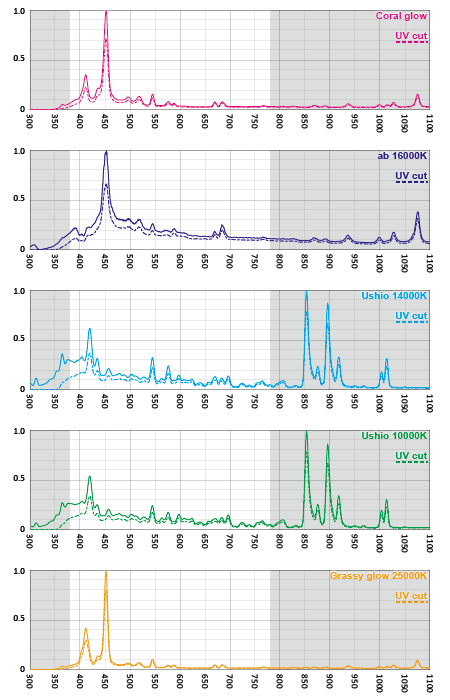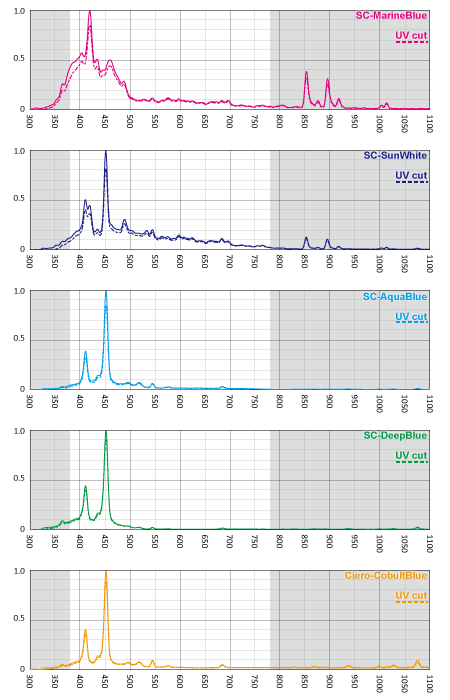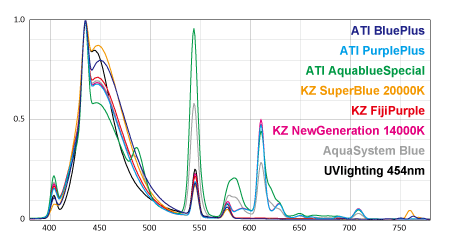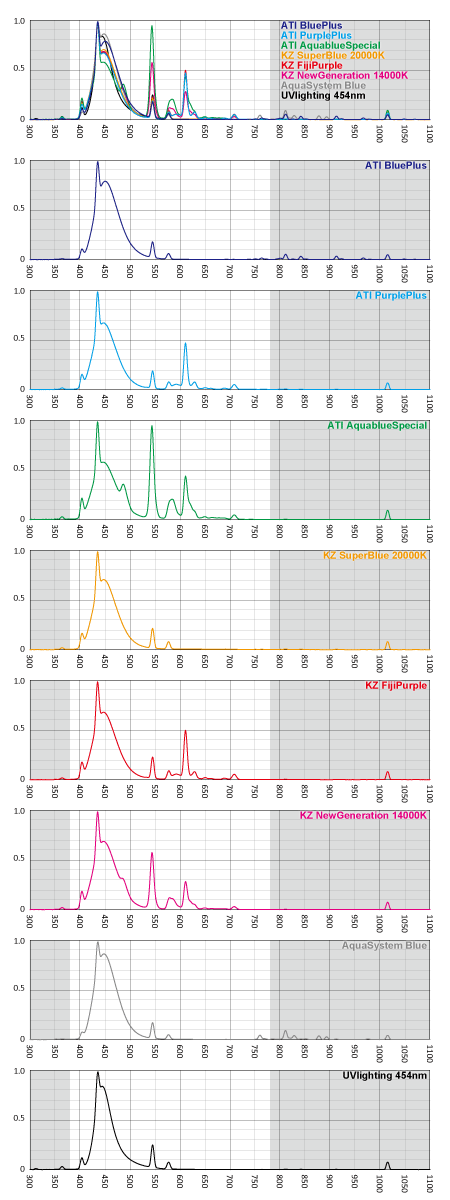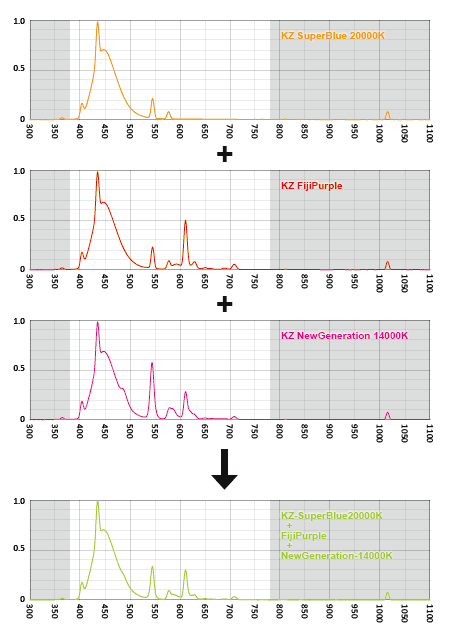注) このページの情報は古いため、2013年現在の各機種の仕様とは異なります。
特にKR90FWの正式版の仕様は白16000KのWチャンネルと白4000KのBチャンネルの調光となります。そのため青だけを点灯させる事はできません。
スペクトル測定?
勿論フルスペも測ってるぜぃ♪
試作のKR90DR/FWも抜かりねぇぜぃ?
あぁ~、案の定設計通りだぜぃ♪
もぉ~、こんな凄ぇの一体誰が作ったんだぜぃ?
聞き飽きただろ~ぅ?
でも本家だって毎回コーラだぜぃ?
KR93SPフルスペクトルエディション2ndロットのスペクトル
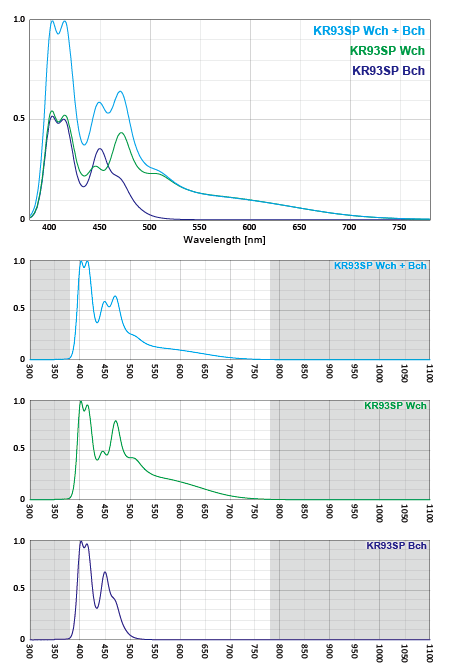
400nmや420nmは特に力を入れて監修してるので、初期ロットよりもさらに光量が強化されてきました。それに伴って早く青系も強化したいのですが、なかなか良いチップが見つかりません。。。まだ時間が掛かりそうです。
KR90DR試作機のスペクトル
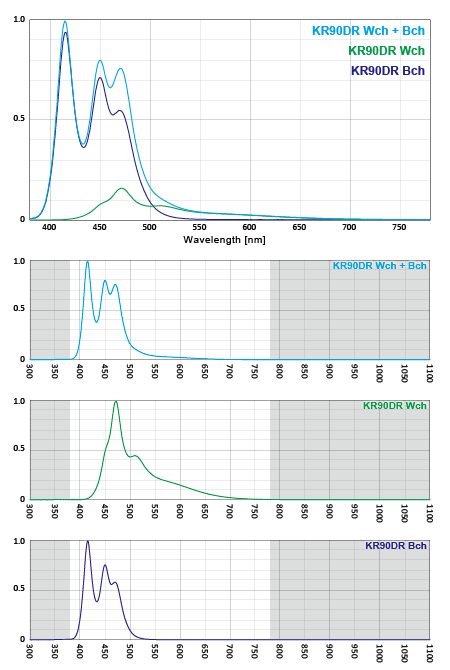
LPS向けDeepReefは水深30M以深をターゲットにしているので、白チャンネルはかなり弱く絞ってあります。一見、スペクトルだけ見ると白が入ってないようにも見えますが、一応1ユニット(12インチ)21素子中3ヶは入ってます。2ユニット(24インチ)で5ヶ。実際の海中スペクトルと比較するとかなり足りませんが、とは言え人間の目には白はどうしても強く見えてしまうので、演色との兼ね合いもあり、これくらいが妥当かなと考えています。
KR90FW試作機のスペクトル
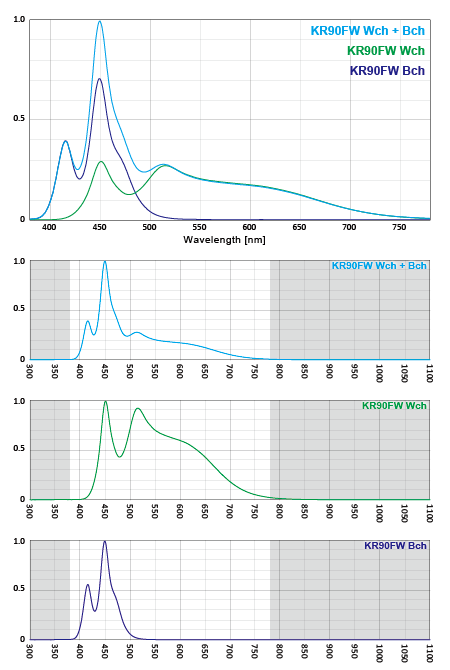
FreshWaterは淡水・水草向けですが、さすがに畑違いな部分もあってか、もう少し再考の余地がありそうです。現在、その道のベテランさんも交えて鋭意テスト中です。結果を見ながら磨いていきます。
ところで、もうひとつ有益な情報をお見せしましょう。
これもかなり気になる部分だと思います。
それは・・・メタハラとフルスペの、放射照度も踏まえたスペクトル比較データです。
KR93SP 18インチ70Wと、コーラルグロー250W、シープロ250W、SCマリンブルーを比較しました。
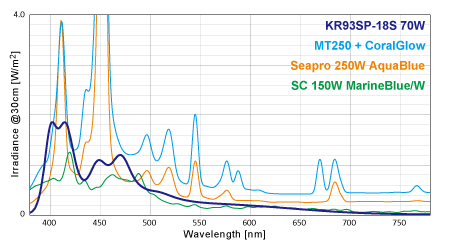
SCとフルスペの比較は今更言うまでもありませんが、250Wクラスのメタハラの場合でも、灯具によってはかなり良い勝負になります。今回は集光の強いMT250を使用したので、直下の測定(上図)ではかなりの差が開いて見えますが、MT250は中心から10cmずれただけでも照度はすぐに半減してしまいますので、広範囲を均一な照度で照らす条件ならフルスペが有利となるでしょう。
それにしても、メタハラが半分以下の消費電力のLEDに負ける時代が来たんですねぇ♪
それも照度だけじゃなく、スペクトルまでもが!
最後に、フルスペに採用されているLED素子の放射照度も測定しておきました。
こんなデータまで見せちゃうなんて、フルスペ透明度高すぎ!笑
フルスペはスコーンと抜けた黒潮を目指します♪
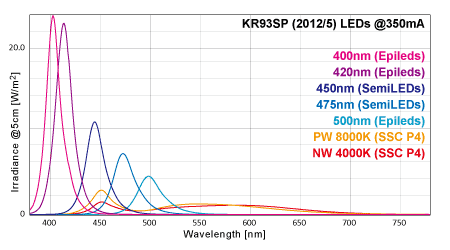
UV系のLED素子は当分これに変わるものは出てこないと思うので、400nmと420nmはしばらく安泰です。巷の素子の軽く倍は出てますからね♪
あと、シアンは現在SemiLEDsチップを採用してますが、そろそろ順次Epiledsチップに切り替わっていくと思います。今までは波長をとるか光量をとるかの葛藤に悩まされてきましたが、今回は波長・光量とも申し分の無いチップが揃う予定です。
あとは青系ですが。。。RebelをKOできるくらいのチップ、どこか作ってないかなぁ。。。
さて。
ようやく次回あたりから、延び延びになっていた秘蔵ネタが書けそうだぜぃ?
ユーザー必見! お待たせMazarra大特集!?
- A-B-C-D各チャンネル駆動電流設定方法
- B-Cチャンネル反転症状(設計ミス)の矯正方法
- 汎用スター基板流用方法
- 純正よりも明るい社外LED素子の紹介
- Mazarraフルスペクトル実験
等々、知りたかったあの情報や、もっとMazarraをいじり倒す丸秘奥義が遂に降臨!
もちろん、すべてはワイルドに自己責任でお願いしちゃうぜぃ?