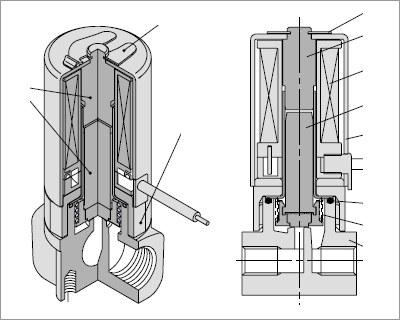昨日の今日で「え?」と思うけど、先ほど水槽に一気にワラワラが湧きました(汗)
「なんか水面に沿ってガラス面が白いなぁ・・・」
と思って近寄ってみたら、鳥肌がっ・・・(曝)

僅かあれだけの海藻の欠片で、こうなったのでしょうか?
海藻に付着していたものに一気に火がついたのか、あるいは元々水槽に潜んでいたものが海藻を栄養源に爆発したのか、詳細は不明です。
で、何故か半数以上が水面から上に登って乾燥しそうだったので、急遽真水を足して水面を少し上げてみました。水質に不満が?
で、多分この子らだと思います。

この写真は昔撮影したもので、縮尺も違ってます。この表示サイズなら×100くらいかな。
コペポーダにも色々居ますが、ちょっとスリムなタイプの子です。
ただ、今ちょうどショップさんにプランクトンを注文していて、その第一便が明日到着します。
こんなに湧くんなら必要なかったかな?(汗)
今年に入ってからずっと放置だった水槽が、実は今すごいことになってます。ヒゲゴケが・・・。
で、何度かトリミングしてみましたが、やはり根本的な処方が必要のようです。
と言う経緯による、ワラワラ出動要請です。
今湧いちゃった子たちと併せて、購入したワラワラと共に、クリーンナップ大作戦を行います。
成果発表は後日っ!