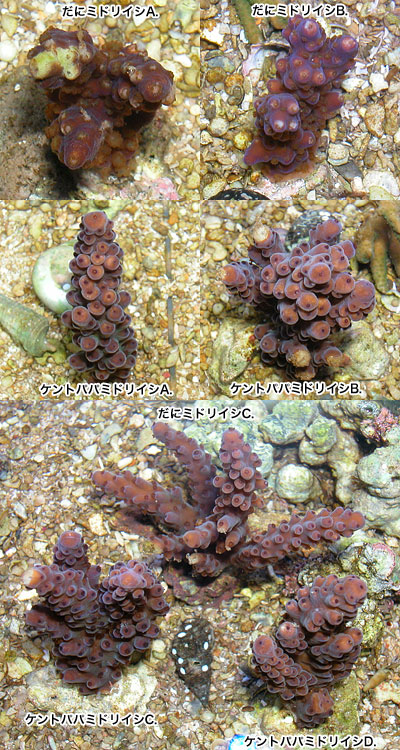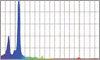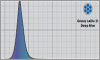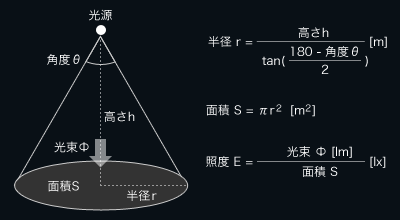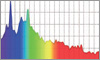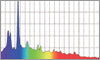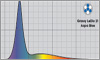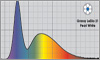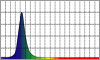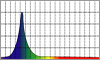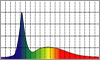いきなりメタハラをLEDに移行しようとすれば、そりゃ無理がある。
まずは、青の移行から始めるのが賢いLEDクリエイターだ。
結論から言えば、スーパークール115 (150W)のディープブルーは、
volxjapanのGrassy LeDio 21 DeepBlue (21W)×2 か、
やどかり屋のエリジオン「閃光」14W ブルー (12W)×2で、光束量的に置き換えが可能であると言えそうだ。もし照度的な置き換えなら1台でも十分だ。しかも、水温上昇が激減し、電気代も超お得になると言うスペシャルボーナスまで着いてくるのだ。
しかし、それ以前の旧製品は素子が古いか効率が悪いかレンズが狭いか、申し訳ないが到底目的は果たせないので、残念ながら現在では選択肢に入ることはないだろう。いっそ、手持ちの旧製品は常夜灯に回してしまおう。
ちなみに、スーパークール115と言えば、かれこれ10年以上の超ロングランだが、さすがに進化のない製品の布教活動はもうそろそろ良いだろう、と覚悟を決めた。これまでも散々オススメしてきたし、メーカーも十分に潤ったことだろう。
ここらでひとつ、業界の未来に期待して、本音トークを暴露しようではないか。
アクアリストは益々救われるがいい。助かるがいい。
しかしメーカーは腐ること無かれ。さらに精進するがいい。
以下のスペック比較を見てすぐに意味を理解した方、善は急げだ。
いまいち判らないけど私を信用すると言うなら、あとに続くがいい。自己責任で(笑)
| ランプ |
SC115 DB
150W/70° |
LeDio21 DB
21W/50° |
エリジオン・ブルー
12W/60° |
| スペクトル |
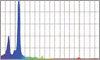 |
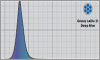 |
無し
LeDio21と同等 |
| 30cm照度 |
4,440 lx |
実測 19,200 lx |
実測 12,200 lx |
| 全光束 |
2,500 lm
換算 615.50 lm |
換算 1180.43 lm |
換算 1149.82 lm |
| 発光効率 |
換算 16.67 lm/W |
換算 56.21 lm/W |
換算 95.82 lm/W |
| 実売価 |
40,000~50,000円 |
16,000~18,000円 |
12,000~13,000円 |
但し、どちらもUVは一切含まれないので、もしUV入りを望むならしばらく待って欲しい。UVブレンドモデルを含む新LeDio7+が、もうすぐvolxjapanから正式に発表されるはずだ。とは言え、光量的には上記2機種には及ばないので、やはりSCの代役は上記機種に任せると良い。そして新LeDio7+UVで、紫外線を補完すれば良いのだ!
尚、このアナウンスはあくまでもSCディープブルーについてのもので、マリンブルー等の明るいランプについては、引き続きSCを支持していきます。当面はね。
とは言え、ひっくり返されないように、メーカーには頑張って欲しいと思います。
そして最後にもうひとつ。
やどかり屋のエリジオン「閃光」をノーブランドと侮る無かれ!
最新LED素子による超高効率と、その驚愕の大光量を、是非騙されたと思って体験して欲しい。
しかも僅か12Wの超省エネ設計。そして更にその軽さにも度肝を抜かれるだろう。
大阪近隣の方は、一度やどかり屋で実機を見てきて欲しい。
以上、この放送は応援市場の提供でお送りしました♪
以下、興味のある方は参考までにどうぞ。
角度・照度・光束の計算のための予備知識
照度 E [lx] = 光束 Φ [lm] ÷ 照射面積 S [m2]
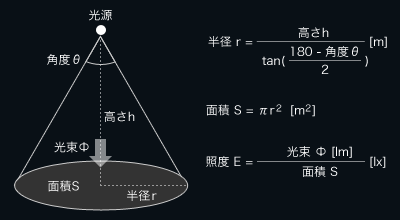
レンズ
° |
照射面積 m2 |
| 30cm前方 |
1M前方 |
| 70 |
0.1386264 |
1.54029334 |
| 60 |
0.0942477796 |
1.04719755 |
| 50 |
0.0614805123 |
0.683116804 |
| 30 |
0.0203000584 |
0.225556204 |
| 25 |
0.0138964176 |
0.15440464 |
このページ内の各値で断わりの無いものはメーカー公称値、実測はショップや私が測定した値、換算は製品のレンズ角度を点光源として逆算した理論値、もちろんレンズの癖・特性等は無視した単純計算によるものです。
比較元各製品スペック
| スーパークール SC115 - 150W/70°(散光) |
| メタハラ |
ディープブルー |
マリンブルー |
サンホワイト |
| スペクトル |
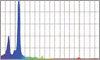 |
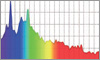 |
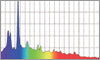 |
| 30cm照度 |
4,440 lx |
31,110 lx |
42,220 lx |
| 全光束 |
2,500 lm |
9,000 lm |
7,300 lm |
| 全光束 |
換算 615.50 lm |
換算 4,312.67 lm |
換算 5,852.81 lm |
| 発光効率 |
換算 16.67 lm/W |
換算 60.00 lm/W |
換算 48.67 lm/W |
| Grassy LeDio 21 - 21W/50° |
| LED |
DeepBlue
青7 |
AquaBlue
青4+白3 |
PearlWhite
青1+白6 |
| スペクトル |
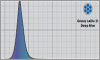 |
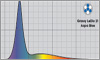 |
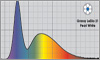 |
| 30cm照度 |
実測 19,200 lx |
実測 16,700 lx |
実測 16,500 lx |
| 全光束 |
換算 1180.43 lm |
換算 1026.72 lm |
換算 1014.43 lm |
| 素子光束 |
換算 168.63 lm |
換算 146.67 lm |
換算 144.92 lm |
| 発光効率 |
換算 56.21 lm/W |
換算 48.89 lm/W |
換算 48.31 lm/W |
| エリジオン「閃光」14W - 12W/60° |
| LED |
Blue
青6+白1 |
BlueWhite
青4+白3 |
White
青1+白6 |
| スペクトル |
|
|
|
| 30cm照度 |
実測 12,200 lx |
実測 10,800 lx |
実測 11,800 lx |
| 全光束 |
換算 1149.82 lm |
換算 1017.88 lm |
換算 1112.12 lm |
| 素子光束 |
換算 164.26 lm |
換算 145.41 lm |
換算 158.87 lm |
| 発光効率 |
換算 95.82 lm/W |
換算 84.82 lm/W |
換算 92.68 lm/W |
| ハイパーアクアムーン - 7.2W/25° |
| LED |
AMC-1B
青6 |
AMC-1BW
青5+白1 |
AMC-1WB
青1+白5 |
| スペクトル |
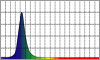 |
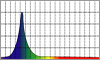 |
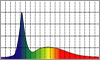 |
| 30cm照度 |
20,000 lx |
18,890 lx |
15,560 lx |
| 全光束 |
換算 277.93 lm |
換算 262.50 lm |
換算 216.23 lm |
| 素子光束 |
換算 46.32 lm |
換算 43.75 lm |
換算 36.04 lm |
| 発光効率 |
換算 38.60 lm/W |
換算 36.46 lm/W |
換算 30.03 lm/W |
| Grassy LeDio 7 - 7W/60° |
| LED |
DeepBlue
青7 |
AquaBlue
青4+白3 |
PearlWhite
青1+白6 |
| スペクトル |
|
|
|
| 30cm照度 |
実測 4,200 lx |
実測 4,700 lx |
実測 5,400 lx |
| 全光束 |
換算 395.84 lm |
換算 442.96 lm |
換算 508.94 lm |
| 素子光束 |
換算 56.55 lm |
換算 63.28 lm |
換算 72.71 lm |
| 発光効率 |
換算 56.55 lm/W |
換算 63.28 lm/W |
換算 72.71 lm/W |

こちらのエントリーもどうぞ♪